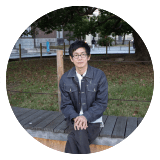Image by: FASHIONSNAP

Image by: FASHIONSNAP
「ゆるふわ大明神」の異名を持ち、長年京都を拠点に大学でファッション論を教える傍ら批評家?キュレーターとしても活動してきた京都精華大学デザイン学部教授の蘆田裕史氏が、「ファッション」や「ファッション論」について身近なものごとから考えるコラム連載。「ファッション論ってなに?」「可視化の時代におけるファッションとは?」に続く第3回は、「美術展とは違う、ファッション展のみかた」について。
ADVERTISING
近年、美術館でファッションの展覧会が開催されることが増えてきています。今年の大きな展覧会としては、「アール?デコとモード」(三菱一号館美術館)、「ルイ?ヴィトン『ビジョナリー?ジャーニー』」(大阪中之島美術館)、「LOVE ファッション─私を着がえるとき」(東京オペラシティ アートギャラリー)などでしょうか。

「LOVEファッション─私を着がえるとき」展より
Image by: FASHIONSNAP
美術館でのファッション展はいまでこそ当たり前のように開催されていますが、こんなにも増えてきたのはここ20~30年のことです。この連載の初回でファッションは学問の対象として捉えられてこなかったと言いましたが、それは美術館においても同様です。たとえば、1980年代には「イヴ?サンローラン」展が批判されるという出来事がありました。しかも、内容がどうこうではなく、開催したこと自体が批判の原因だったのです。その言い分としては、「ファッションはビジネスなんだから、存命中のデザイナーの展覧会を美術館で開催するなんてありえない!」というものです。
その後、ファッション展は徐々に世間に認められるようになります。同じくメトロポリタン美術館で2011年に開催された「アレキサンダー?マックイーン─野生の美」展は、来場者が60万人を超えるほどの盛況ぶりでした。この展覧会はマックイーンの死後に開催されたものなのでサンローラン展と単純な比較はできませんが、ブランド自体は存続していたという事実をふまえると、現代のファッションデザイナー/ブランドの美術館での展覧会が世間で認められた証だと言えるでしょう。
日本でも(一部の)ファッション展は高い集客力を持つものになってきています。一昨年、東京都現代美術館で「クリスチャン?ディオール、夢のクチュリエ」展が開催されましたが、これは28万人を超える入場者数があったようです。*?
僕は「美術館でファッション展を開催するなんてありえない」という意見にはもちろん与しません。けれどもファッションの展覧会と美術の展覧会は異なるのは事実です。その違いについて少し考えてみたいと思います。(文:蘆田裕史)
衣服の固有性は「情報量の少なさ」
たとえば、ここに巨匠の手になる一枚の絵画があるとします。これを「鑑賞」するための最高の環境はどのようなものでしょうか。ルーブル美術館のように空間自体が独特の雰囲気を持つ歴史的建造物に置かれるか、あるいはニューヨーク近代美術館(MoMA)のようにホワイトキューブとよばれるニュートラルな白い空間に置かれるか、どちらを選ぶべきか。「ホワイトキューブ」という概念はMoMAに端を発しますが、これは作品以外の情報をノイズとみなし、作品だけに目を向けてもらうための空間と言えるでしょう。
どちらの空間が適切かは作家やキュレーターの目的にもよるので一概には言えませんが、美術作品の展示に関して言えば、20世紀は後者のホワイトキューブが理想とされてきました。作品を空間から引き剥がし、作品それ自体を見るのが望ましいという考えは十分理解ができますし、もしかしたら美術の場合はそれでもよいのかもしれません。けれども、ファッションにはファッションの固有性があります。
ファッションの固有性をどのようにとらえるかは観点によって変わると思います。たとえば美術館でのファッション展が批判されるとき、「ファッションはビジネス」だからと言われることもありますが、美術も実際に作品の売買がなされ、それによって作家やギャラリストが生計を立てていることをふまえれば、ビジネスであることは間違いありません。むしろ僕がつねに念頭に置いているのは、衣服の「情報量」の少なさです。
たとえば、あなたの好きな一本の映画と、あなたの好きな一枚の衣服の内容を言葉で説明しようとしてみてください。おそらく映画については色々と語れるはずですが、衣服について語るのが難しいことがわかるのではないでしょうか。映画には物語、演技、演出、音楽、編集などさまざまな要素があり、とりわけ物語はもともと言語によって作られているため、言葉で説明することが比較的容易です。また、作品が長時間にわたって展開されるため、それだけ情報量は多くなります。一方、衣服はそれ自体から物語を受け取ることもできず、時間性もはらんでいないため、そこから情報を読み取ることがきわめて難しいと言えるでしょう。
衣服の情報量が少ないことは、ファッション展において作品そのものだけを対象として鑑賞することがきわめて難しいことを意味します。
ファッション展における「セノグラフィ」の重要性
さきほど言及したディオール展の出展作品は1500点以上もあったそうですが、仮に作品1点を1分間かけて鑑賞するとしたら、1500分(25時間!)かかることになります。つまり、展覧会自体が作品すべてをじっくり見てもらう設計になっていないのです。では、私たちは何を見るべきなのか。その鍵となるのが「セノグラフィ(scenography)」という概念です。
僕はまだセノグラフィのうまい訳語を見つけられていないのですが、文字通りに訳すなら「情景(scene)の描写法(graphy)」、つまり空間をどのように作り出すか、ということですので、ひとまず「空間演出」と訳すことができるでしょう。ディオール展では建築家の重松象平氏がセノグラフィを担当し、壁のみならず天井までも作品を散りばめる空間が作られていました。そうなると当然、近くで見ることのできない作品も出てきます。
「クリスチャン?ディオール、夢のクチュリエ」展での展示の様子 Video by FASHIONSNAP
ひょっとしたらこのような展示方法は、作品ひとつひとつを見たいと思う鑑賞者にとっては歓迎できないものなのではないか、という疑問を持つ人もいるかもしれません。その気持ちは理解できるのですが、ファッションのもうひとつの固有性を考えるとこれがむしろ正解とも言えるように思われます。それは、ファッションはモノ(=衣服)だけで完結するわけではない、ということです。
モノだけでは不十分、イメージを作ってはじめて完成する「服」
もし「20世紀前半を代表するデザイナーは誰ですか?」と尋ねられたら、おそらく多くの人がガブリエル?シャネル(Gabrielle Chanel)の名前を挙げるのではないでしょうか。シャネルは活動的な女性のための服を作り、女性が社会に進出する一助となった、としばしば言われますし、それは間違いではないのでしょう。けれども、服飾史家のヴァレリー?スティール(Valerie Steele)は、シャネルの服と同時代のデザイナーの服は、キャプションなしではわからないくらい似ていたと指摘しています*?。それなのになぜ、シャネルがこれほどまでの知名度を得ているのか。それは「イメージ」をうまく作り、それが伝播したからだと言えます。
ファッションブランドはなぜルックの撮影をするのでしょうか。なぜファッションは雑誌やSNSというメディアが強いのでしょうか。それはひとえにイメージがモノと同じくらい重要だからです。ファッションという領域では、服を作るだけでは不十分で、イメージまで作り上げてはじめて完成をみるといっても過言ではありません。これも衣服の情報量が少ないことに起因しています。
美術の場合、たとえばピカソの作品が展覧会のカタログに掲載されるとして、それを撮影する写真家によって作品の見え方がまったく異なるということになると、おそらく問題になるでしょう。それは作品それ自体で完結しているために、第三者の手でイメージが操作されることが望まれていないからです。けれどもファッションの場合は、誰がその服を着て、どんな場所で、誰が撮影するかによって見え方がまったく変わってきますし、それが肯定的に捉えられています。私たちは服からだけでは十分な情報を得ることができないのですから。
ひるがえって、ファッション展も同様です。美術作品において理想とされるような、ホワイトキューブに作品を置くような展示をしてしまうと、ファッション展は途端に「分からない」ものになってしまいます。私たちはファッションをモノだけで見ることには慣れていないので。そう考えると、服の見せ方/伝え方に長けたラグジュアリーブランドが展覧会を行うとき、なぜセノグラフィを重視して、服の背後にある情報を伝えようとするのかがよく理解できるのではないでしょうか。
ちなみに、国外に目を向けてみると、アントワープのモード美術館(MoMu)は明確に「セノグラフィ」という言葉をかかげて、それを重視しています。
MoMuの展覧会は、没入観のあるセノグラフィを特徴としています。鑑賞者であるあなたは単に展示品を見るのではなく、デザイナーの世界やテーマに入り込むことができます。展示スペースは展覧会ごとに完全に姿を変え、訪れるたびにまったく異なる体験が味わえるのです。*?
日本の美術館では、セノグラフィという概念に触れられること自体があまりありません。近現代美術がホワイトキューブを理想としてきたので仕方ない側面があるのですが、今後もファッション展が増え続けるのであれば、セノグラフィはもっと重視されるべきだと思われます。
さらに言えば、昨今のラグジュアリーブランドによるファッション展では、どのブランドもイメージのみならず「物語」を提示しようとしています。ブランドの歴史、製品の素材や、それが作られる過程、品質の検査方法、あるいは職人が展示会場で実際に制作する場面を見せるパフォーマンスなどです。これらによって、そのブランドの製品がどれだけ豊かな物語をもっているのか、それを視覚的に補完しようとしているのです。

2004年にメトロポリタン美術館で開催された「Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the Eighteenth Century」展の展示風景。18世紀のファッションや家具の背景にある人々の生活の様子が、セノグラフィを通して豊かに表現されている。
Image by: Scott Eells/Getty Images
良いファッション展の条件とは?
さらにさらに付け加えて言うならば、展覧会の固有性も考える必要があるでしょう。展覧会はショップと異なり、服を触ったり試着したりすることができません。それゆえ視覚を中心的な体験に据えざるをえません。近年、美術の展覧会では撮影を目的とした鑑賞態度が批判されることがしばしばありますが、視覚優位の展覧会においては仕方ない側面もあるでしょう。展覧会は本とも違うのですから。もし、展覧会においても頭で考えることがより重要で、視覚的な経験が重要でないのであれば、展覧会を企画するよりも本を書いた方がよいでしょう。
さきほど、ファッションではモノだけではなくイメージも重要だと言いましたが、それは「モノが重要ではない」という意味ではありません。その作品がそこにある「必然性」が欠けていては、やはり展覧会としての完成度が高いとは言いがたいように思われます。
ファッション展に関して知人と話をしているなかで、(その人の周りでは)今年東京で開催された「ロエベ クラフテッド?ワールド展 クラフトが紡ぐ世界」の満足度が高い一方で、同時期に開催された「LOVE ファッション─私を着がえるとき」の満足度があまり高くなかった、という話を聞いたのですが、おそらくその一因は、いま述べた「その作品が置かれることの必然性」にあるのではないでしょうか。
「LOVE ファッション」展は5年ほど前に開催された「ドレス?コード?─着る人たちのゲーム」展と同様、ファッションに関わる理論をベースに作られた展覧会です。つまり、僕がここで書いているような「ファッション論」を展覧会に落とし込んだものと言えます。文章の固有性は「読んで理解できること」なので、いまあなたが読んでいるこの文章に対して「視覚的に楽しめない!」と不満を持つ人はおそらくいないと思いますが、展覧会は違います。展覧会は読む(頭で考える)ことが第一にあるのではなく、まずもって見ることが重要です。となると、同じく「理論の提示」であっても、視覚的に理解できる仕組みを作る必要があります。また、理論が先行してしまうと、展示作品が「理論を説明するために適切なもの」になり、作品それ自体が鑑賞の対象となるのではなく、作品の背後にある理論が優位に立ってしまいます。





「きれいになりたい」をテーマに展示された作品(「LOVEファッション─私を着がえるとき」展)
Image by: FASHIONSNAP
つまるところ、バランスが大事という陳腐な結論になってしまうのですが、モノとイメージのバランスがうまく取れなければ、良い展覧会にはならないでしょう。その一方で、セノグラフィにこだわるには予算が必要なので、日本の美術館や個人の企画ではなかなか難しいという実情もあるのは理解しています。良い展覧会を作るのにはお金がかかる、けれども文化にお金をかけることがますます難しくなってきている、という問題の解決策を提示することはここでは(というか僕には)できませんが、まずはセノグラフィに対する意識向上は目指したいところです。
ということでまた来月に!
*??『2023年度 東京都現代美術館年報』より。
*? ヴァレリー?スティール『ファッションセオリー——ヴァレリー?スティール著作選集』(平芳裕子?蘆田裕史監訳)アダチプレス、2025年
*??MoMu 公式サイトより。
★今回のテーマをもっとよく知るための推薦図書
?難波優輝『物語化批判の哲学——〈わたし〉の人生を遊びなおすために』講談社、2025年
(物語について考えたい人のために)
?平芳裕子『東大ファッション論集中講義』筑摩書房、2024年
(第1回でも推薦図書に挙げたのですが、ファッション展についてきれいに整理されているので。)
?メトロポリタン美術館で開催された「Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the Eighteenth Century」展のカタログ
(本文は読まなくていいので展示写真だけでも見てほしい!リンク先から無料でダウンロードできます。)
edit: Erika Sasaki(FASHIONSNAP)
illustration: Riko Miyake(FASHIONSNAP)
1978年京都生まれ。京都大学薬学部卒業、同大学大学院人間?環境学研究科博士課程研究指導認定退学。京都服飾文化研究財団アソシエイト?キュレーターなどを経て、2013年より京都精華大学ファッションコース講師、現在は同大学デザイン学部教授。批評家/キュレーターとしても活動し、ファッションの批評誌「vanitas」編集委員のほか、本と服の店「コトバトフク」の運営メンバーも務める。主著は、「言葉と衣服」「クリティカル?ワード ファッションスタディーズ」。
??ゆるふわファッション講義
第1回:ファッション論ってなに?
第2回:可視化の時代におけるファッションとは?
第3回:美術展とは違う、ファッション展のみかた
第4回:「黒の衝撃」から辿る、日本の90年代ファッション再考
第5回:インターネット普及以後の日本ファッション??平面性と物語性
第6回:私たちは“二つの身体”を持っている──ヌード、義足、厚底シューズ
最終更新日:
ADVERTISING
PAST ARTICLES
【ゆるふわファッション講義】の過去記事
RELATED ARTICLE
関連記事
READ ALSO
あわせて読みたい
足球即时比分,比分直播
アクセスランキング